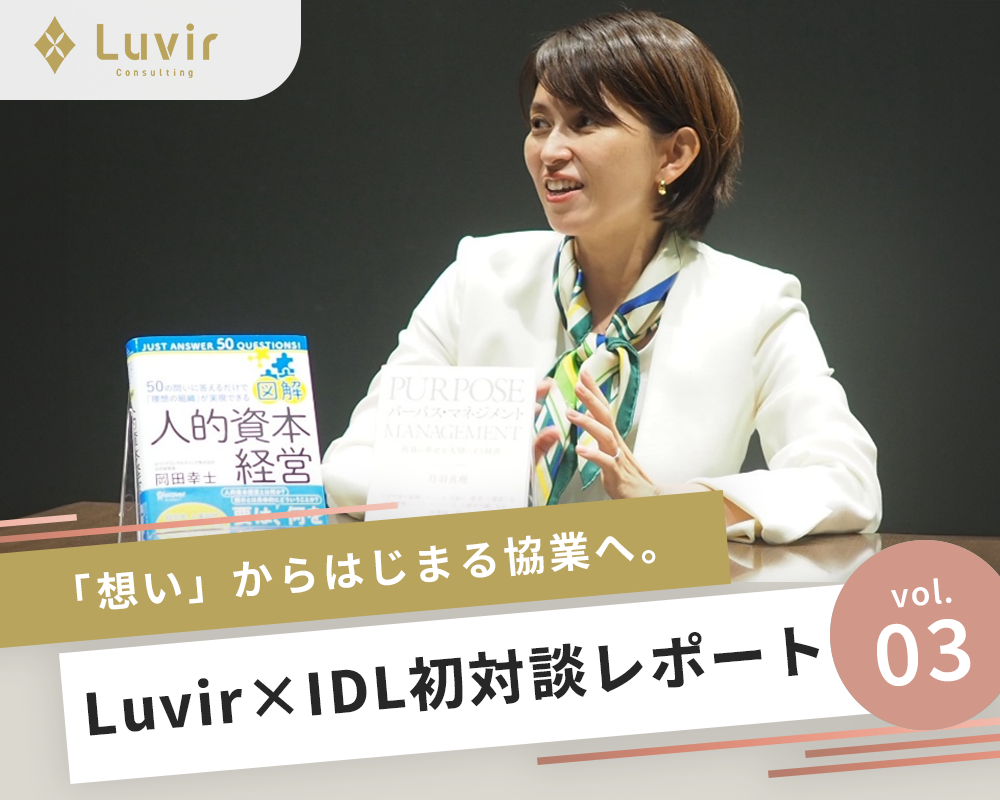対話から立ち上がる組織設計。
「アイディール」が起こす変革のプロセス
対談を重ねる中で、Luvirとアイディールの協業ビジョンは、より具体的な輪郭を帯びはじめる。
岡田氏が「理想の職場の実現例」と語るアイディールは、どのようにして組織をつくりあげてきたのか──。本セッションでは、アイディールの組織づくりに迫りながら、ウェルビーイング経営の可能性を探る。
やらされ感のない組織づくり
奥地:丹羽さんにすごくお話を聞きたかったことがありまして。やっていて楽しい仕事と、やらなきゃいけない仕事の割合って、どんな感じですか。
僕自身、前職では「やりたい仕事」が3割、「やらなきゃいけない仕事」が7割くらいの感覚だったんですけど、それでも結構満足していたんですよね。でも、理想を言えば、やりたい仕事だけで10割あれば最高だなと思っていて。そのあたり、丹羽さんはどう考えていますか?
丹羽:うーん、「やらなきゃいけない仕事」って何だろうな…って感じですね。
中川:やりたい仕事が10割ってことですか?
丹羽:10割とは言い切れないかもしれませんけど、基本的にみんながやりたくない仕事ならやらなくていいと思ってます。乗り気じゃないことは、できるだけ排除していく方針なので。誰かがやりたいと思ってるなら、その人がやればいいですし。
たぶんうちのメンバーに聞いても、「これはやりたくない」という仕事はあまりないと思います。とはいえ、それぞれ得意な分野や極めたいテーマは違うので、中には「こういうテーマにすごく取り組みたいけれど、今は案件が少なくて別のことをやっている」というケースはあると思います。でも、そのような場面でも、全然やりたくないものを仕方なくやっている、という状況ではないと思います。
中川:やりたいことをやる方が、パフォーマンスも上がりますからね。
丹羽:そのあたりの考え方が似ていますよね。そういえば、さっき中川さんがおっしゃっていた、「会社を真剣な遊び場に」という話にも、すごく共感します。うちにもそれに近いカルチャーがあって、「明るく・楽しく・前向きに」というスローガンがあるんです。毎週月曜の朝のミーティングの最後に、みんなでそれを唱和するんですよ。「ATM!」って(笑)。
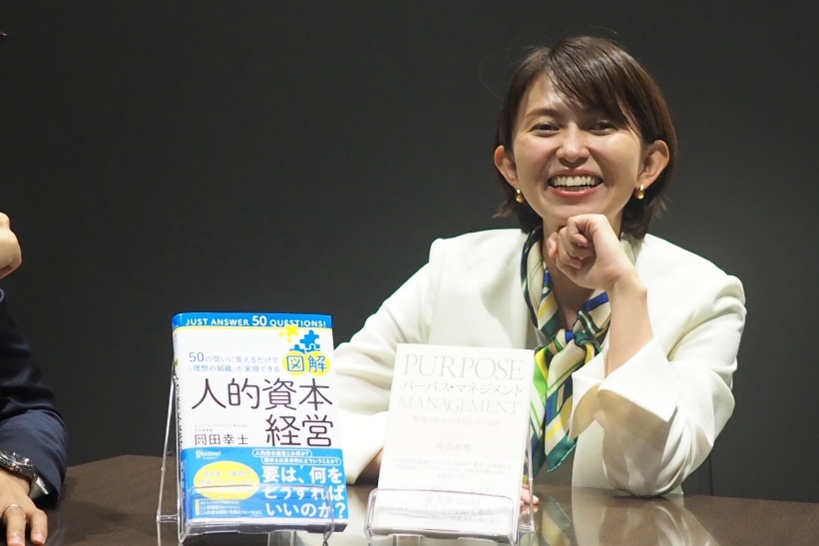
中川:ATM! お金下ろすやつみたいですね(笑)。
丹羽:たしかに(笑)。やっぱり、世の中的には「仕事は苦行だ」という価値観が一般的にあるじゃないですか。つらいことをするからお金がもらえる、みたいな。それを変えていきたいという想いがあるんですよね。
中川:分かります。「サザエさん症候群」ってご存知ですか。日曜の夜に「明日会社か…」って憂うことなんですけど。僕はそれを「少年ジャンプ症候群」に変えたいんですよ。
「月曜日はジャンプ発売だー!」って、日曜日の夜からもう次の日が待ちきれないような状態に変えたくって。そういう気持ちになれる仕事じゃないと、やっぱりパフォーマンス上がらないじゃないですか。やらされ感を徹底的に排除しないと。
丹羽:働くことに対する前提の価値観を変えていきたいですよね。

対話で築く“等身大”の組織運営
岡田:会社を大きくしていくことについては、どれくらい重要視していますか?
丹羽:正直、上場しようとは全然思ってないんです。
でも、社会へのインパクトを大きくしたいという気持ちはありますね。
ものすごいスピードで100人、200人に増やそうとも考えていませんが、去年あたりから採用はしっかりやろうという話になっていて。毎年3〜4人くらいは増えています。
岡田:組織拡大と楽しさのバランスって難しいですよね。今いらっしゃるメンバーの方々も、丹羽さんと同じような考え方をされてるんですか?
丹羽:そうですね。組織をどういうスピード感で大きくしていくかは、みんなで話し合っています。たとえば「2030年にはこのくらいの規模に」といった目安はあるんですけど、仮に今年採用がうまくいかなかったとしても、「それが達成できないと絶対ダメ」とは誰も思っていなくて。数字を達成すること自体が目的ではないので、「多少前後しても全然OK」という空気感はあると思います。
岡田:なるほど、そういったスタイルでされてるんですね。
奥地:そういう話って、事前にアジェンダを立てて「この日この話をしよう」と決めてやるんですか? それとも、普段みんなで集まってる中で自然と出てくる感じですか?
丹羽:どちらもありますね。
毎週月曜の午前中に、全員で集まっていろんな話をする時間があって、そこに誰かがアジェンダを書き込めば、そのテーマについて話し合います。
ただ、普段の定例では時間が足りないような議題は、四半期に一度、まる二日とっているのでそこでじっくり話すことが多いですね。
岡田:かなりしっかり、対話の時間を時間取られてるんですね。
プロセスに価値を置くコンサルティング
中川:私からも少し伺いたいのですが、プロジェクトの具体的な進め方について、もう少し詳しく教えていただけますか?プロジェクトの設計や立ち上げ方、どのように関わっていくのか、最終的なゴールの設定の仕方など…。
そうした“ハードな部分”について、ある程度は見えてきた気がしているのですが、実際はどうなんでしょうか。
丹羽:そうですね、ただ内容はほんとにケースバイケースなので、何を代表的なものとしてご紹介すればいいのか分からないですけど…。
中川:プロジェクトの中には、アウトプットそのものが価値になるケースもありますけど、それ以上にプロセス自体がキーになるものも多いですよね。
特に御社のようなプロジェクトだと、後者――プロセスが大事という印象があります。完成物じゃなくて、作っていく過程こそが重要というか。
丹羽:そういう意味では、私たち、そもそも「納品物」がほとんどないんですよ。最終アウトプットを提出するというよりも、そのプロセス自体に価値を出すスタイルです。
たとえば「パーパス(存在意義)」の言語化をするにしても、最終的に言葉を紡ぎ出すのはクライアント自身です。必要であればコピーライターさんなどに入ってもらうこともありますが、それでも私たちが決めるわけではなく、「クライアントの言葉をどう表現するか」なんです。 だから、明確な資料が出来上がることも少ないし、「これが完成したから終わり」というゴールもあまりない。プロセスそのものが価値で、それに全力で向き合っています。

中川:その「プロセス」って、具体的にどんなものがありますか?なにか王道パターンがあるんでしょうか。
丹羽:王道もあります。たとえばパーパス策定のプロジェクトでは、基本的には「お客様自身が考える」ことをサポートするプロセスコンサルティングになります。
ただ、いきなり「考えてください」と言っても難しいので、私たちがファシリテーションします。経営陣だけでなく、多くの社員を巻き込みたいというニーズも多いので、状況に応じてプロセスを丁寧に設計していく形です。
中川:たしかに、急には出てこないですもんね。
丹羽:そうなんです。以前大阪でご一緒した会社では、約1年かけて取り組みました。まずスタートは、全役員にエグゼクティブコーチングを行い、「どんな会社にしたいか」「今抱えている課題は何か」といったテーマを掘り下げていくところから。その上で、社員数十人規模でワークショップを開催し、会社の歴史や個々の価値観を振り返りながら、「自分たちはなにが強みで、どういう会社にしていきたいのか」「2045年の理想の姿はどういうものか」といったビジョンを考えてもらいました。「その未来を実現しようとする私たちは、何のために存在しているのか?」という問いを立てて、全員でパーパスを考えていくんです。
中川:なるほど。
丹羽:とはいえ、みんなが納得して「これだ!」と合意できるまで持っていくのは結構難しくて。1人でも「なにか違う」と思っていると、前に進まなくなることもあります。だから私たちは、そのプロセス設計が何よりも重要だと考えているんです。
毎回プロジェクトに合わせて、「次のワークショップでは、どういうことを考えてもらうと良いだろうか」「こういう視点で議論をしてもらおう」と柔軟に設計するのが私達の仕事です。
ファシリテーション自体ももちろんやりますが、話がうまいかどうかよりも、その場の空気や状況に対応できるかの方が大事だと考えています。お客さんと相談して、こういう観点を入れた方がいいんじゃないかとディスカッションしながら、進め方を決めていくんですよね。
中川:そのスタイルって、ハードなテーマにも全然応用できますよね。たとえば、今まさに奥地さんと一緒に提案している会社は、表向きのテーマは「グループ人事全体の機能・役割設計」というめちゃくちゃハードな内容なんですが…。
でもそのカウンターの想い、裏テーマとしては、「そのプロセスを通じて各人事担当者のマインドを変えたい」というものがあって。それこそ御社のようなプロセス重視のアプローチがすごくはまる気がするんですよね。今後もしご一緒できるなら、ぜひ修行させていただきたいです。
丹羽:私たちは、たとえば「パーパス」のようなフレーズが生まれたとき、それを社員がいいなと共感し、自分ごととして捉えられるようになる、というプロセスをよくご支援しています。制度設計にしても、「やらされ感」でやるのではなく、担当者が楽しみながら関わっていくと、完成した制度への思い入れや熱量がまったく変わってくるんですよね。そういった部分で、うまくコラボできたらいいなと思っています。
奥地:または、一部で取り入れる形でもいいかもしれませんね。たとえば人事制度や組織開発の案件で、うちは最初にトップインタビューを入れるんですが、そこに少しエグゼクティブコーチング的な要素を入れるだけでも、トップの視座がグッと引き上がると思います。
丹羽:たしかに上の人が視座を上げるだけで、大きく変わってきますよね。
保守的な組織では「変革の火種」を育てていく
岡田:そういえば、最近よくいろんな企業で「中間管理職が30年前の価値観に凝り固まってて困っている」という話を聞くんですが、そういう相談を受けたときってどう対応されてますか?
奥地:そもそもパーパスを掲げようと思う経営者自体が、もうある程度視座が高いというか、イケてる経営者が多い気がしていて。
僕もこの前、「コンサルなんて要らない」「パーパスって何?」という感じの、すごく保守的な会社に出会いまして。地方の中ではトップクラスの企業なんですが、価値観が完全に昔のままなんです。

中川:ほんと、「なんとなく回ってるから変える必要ない」みたいな空気感があるんですよね。でも、それじゃ視座が上がらない。
丹羽:そういう場合って、たとえば経営者自身の価値観や考え方が、無意識に組織に影響していることが多いんです。
だから私たちはまず、「その社長さんがどう考えているのか、ぜひ聞かせてください」と、コーチング的に関わります。ただ、経営者本人が「自分の価値観が時代遅れかも」とか、「若手から違和感を持たれてる」と自覚してないこともある。そういう場合は、周囲の社員にインタビューして「こういう声がありましたよ」とフィードバックすることもあります。
岡田:よくある構造として、社長が圧倒的な権限を持っていて、「社長の言うことだけ聞いておけばいい」という空気が役員層に蔓延してるケースはありますよね。
そういう企業では、やらされ感が上から下まで組織全体に根付いてしまってる。それを、社長自身が気づいていないことがほとんどなんですよ。
丹羽:そういうときも、もちろん「誰がこんなことを言ってましたよ」なんて個別には言いませんけど、「こういう意見が出ています」という形でちゃんとフィードバックします。ただ、大事なのはその会社の中に、「旧来型のあり方を本気で変えたい」と思っている人がいるかどうか。もし誰一人としていなければ、正直変えるのは無理なんです。だからこそ、そういう“変えたい”という思いを持った人がいたら、その人を全力でサポートします。

奥地:「どこかに火がついてる人」がいるかどうかなんですね。
丹羽:そうそう!でも、変えたいと思っている人が社内に1人だけだと、なかなか組織は動きません。だから私たちは、まずその人に「仲間を見つけましょう」とお伝えして、社内で変革を担うチームを立ち上げてもらうようにしています。
そのチームがいないと、いくら「変わらなきゃダメだよね」と外から言っても、なかなか動かない。だからこそ、「一緒にやりませんか?」とサポートしていくんです。
岡田:なるほど。じゃあホットライン作ったらいいかもしれないですね。「うちの会社、ヤバいと思ったらここまで!」みたいな。

コーチングはプロジェクトの潤滑油
中川:あるクライアントに、うちのコーチング資格を持っているメンバーが、試験的にコーチングを導入したんですよ。
そのときのフィードバックがすごくよくて、お客様からも「これはありがたい」と言っていただけました。プロジェクトへの向き合い方が大きく変わったし、いつも心の中でモヤモヤしていたものを、コーチングで引き出されて言語化できたことで、「自分はこう考えているから、こういう行動を取らないといけないんだな」と整理できたそうです。そのときに、「もっとコーチングの機会が欲しい」ということを言われました。
丹羽:少しの投資で、プロジェクトの成果や、関わる人の意識・行動が大きく変わるなら、ものすごく効果的ですよね。
岡田:例えば、Luvirの社内メンバーが、プロジェクトの中で「これってなんか違うな…」とモヤモヤすることがあったとして。そういうのを、誰かに話して吐き出せるだけでもめちゃくちゃ助かるんですよね。そうしたモヤモヤって、組織内の人には言いづらいこともあるから、外の方に聞いてもらえる場があると本当にありがたい。
原田:ぜひお願いしたいです。モヤモヤしていることばっかりなので!でもこうして、ちゃんと未来の話ができてるのは嬉しいですね。
組織の変革は、押しつけるものではなく、対話とチェンジマネジメントの積み重ねから生まれる。異なる立場でありながらも、両者の目指す理想には多くの共通点があることが、確かに見えてきた。
最終回となる次回は、これまでの対話を通じて見えてきた両社の可能性と、「これから何をしていくのか」という未来への展望に迫ってゆく。