なぜ、あなたと?協業の理由と見えてきたビジョン
対話を通じて、両社の間にある価値観やスタンスの共通点が徐々に明らかになってきた。司会の原田氏の問いかけによって、話題は「そもそも、なぜ“協業”という選択肢が生まれたのか」へと向かっていく。いったい何がきっかけとなり、両者は今、手を取り合おうとしているのか──。
協業の理由は、ケイパビリティだけじゃない
原田(司会):ここまでお話を伺ってきて、両者に多くの共通点が見えてきたところだと思います。そこで改めて、両者がなぜ協業をしようと思ったのか、そのきっかけや想いをお聞きしたいです。
奥地:ひとつ大きな理由としては、組織としてのケイパビリティ――いわば“強み”の補完ができることです。単純化するとソフト面とハード面、それぞれに得意分野があって、それがうまくかみ合うんですよね。
…と、そういった利点はありますが、それ以上に大きかったのは、やはり丹羽さんと最初に話したときの直感的なフィーリングです。
最初にお会いしたとき、「あれ、昔から知ってたっけ?」と思うくらい違和感がなかったんです。中川さんや岡田さんともそういう関係性だったんですが、丹羽さんともまさにそんな感じで。
丹羽:ほんとに、それくらい自然でしたよね。
奥地:もちろん組織としてのケイパビリティでの利点もありますが、根っこの部分での共通感覚がすごく大きいんです。目指している組織のあり方や、描いている世界観がとても近い。だから、感覚だけでなく、構造的にも相性がいいと思ったんです。

原田:「目指すところが同じで、ケイパビリティが違う」というのが協業の決め手だったんですね。それに加えて、丹羽さんとフィーリングが合ったと。
奥地:そうそう!一番最初に「この人たちと一緒にいたらなんだか面白いことができそうだ」ってワクワクした感覚があって。そこがすごく大きかったです。
協業の話は他にも色々あるんですけど、実際に話してみてワクワクするかどうかって、本当に大事なんですよね。それがあるかどうかで、全然違う。
岡田:会社として相性がいいかどうかと、カウンターパートとして相性がいいかどうかの両方がそろってないと、長続きしないですからね。
奥地:あとは、たまたま共通の案件ベースで話す機会があったことですね。偶然ですが、それが協業の話につながるきっかけになった部分もあります。何となくの盛り上がりで協業の話が出ても、結局なにも生まれないケースもあるので。
岡田:最初は盛り上がるけど、実にならないことって、よくありますよね。
「理想の職場」の実現例がそこにあった
原田:中川さんと岡田さんは、最初に奥地さんから協業の話があったとき、どんな印象を持ちましたか?
中川:最初は、なんとなく「ハードとソフトで補完し合えそうだな」と思っていました。でも実際に会って話したときに、やっぱり「コンサルの本質ってチェンジマネジメントだよね」という共通の理解があると感じて。それが本当の意味でのフィット感につながった気がしています。テーマは違っても、最終的に目指すところが似ていたというか。
岡田:そうですね。私の視点から言うと、人的資本経営の文脈では、その源流にあるのは“パーパス”だと思っていて。私たちはこれまで、そのあたりにあまり手をつけてこなかったので、アイディールさんとなら、そこをうまく補い合えると感じました。それから、「自分が作りたい職場のイメージ」をアイディールさんがすでに実現されているなと思ったんです。なので、一緒にやることで成功も失敗も学ばせてもらえる気がして、すごく勉強になりそうだと感じました。

奥地:うん。そういう意味ではたしかに、Luvirのメンバーがすごく成長しそうだなという感覚がありましたね。アイディールさんと一緒に何かをやっていけば、自分自身も視野が広がるし、なにかいい刺激を受けられるんじゃないかって。
岡田:人事ってある意味、パーパスの文脈でいうとすごく特殊な立ち位置なんですよね。だからこそ、もっと視点を変えていかなきゃいけない。その一環として、いずれは人材の「出向」や「相互派遣」もやっていきたいと思っています。
丹羽:やりたいですね!
パーパスの3ステップをより強固なものに
原田:アイディールさんから見て、Luvirと組むことの良さは、何かありますか?
丹羽:Luvirさんは幅広く事業を展開されているので、じつは私たちも全貌をまだ掴みきれてないんです。
中川:たしかに、かなり幅広く展開してますからね…。
丹羽:でもだからこそ、これからもっと広がっていくんだろうなという可能性を感じてます。例えば、「パーパス経営」に関する3つのステップというものがあって、①発見、②共鳴、③実装というステップですね。
発見は、自分たちが何のために存在するのかを再発見し、言葉にするプロセス。共鳴は、社員一人ひとりがその言葉に共感し、「自分ごと」として向き合える状態をつくること。
原田:まさにアイディールさんの得意分野ですね。
丹羽:はい。でも3つ目の「実装」という、きちんとパーパスで言っていることを実際の経営や事業に落とし込んでいくフェーズになると、私たちのケイパビリティではカバーしきれない部分もあって。その部分に、Luvirさんの得意領域がフィットするのでは、と思っています。例えばパーパスに沿ったサービスづくり、組織構造の再設計、人事制度との連動など、そこがアラインしていないと、それこそ「絵に描いた餅」になってしまうので。
原田: なるほど…。現場の制度や構造とつながって、初めて意味を持つと。
丹羽:ええ。そこまでやって初めて、パーパスが本当に経営の軸として機能すると思うんです。なので、もし一緒に取り組めれば、私たちとしても「パーパスを掲げて終わり」ではなくて、しっかりそれを実践している会社をつくるところまで伴走できるようになりますし、非常に価値のある協業になると思っています。
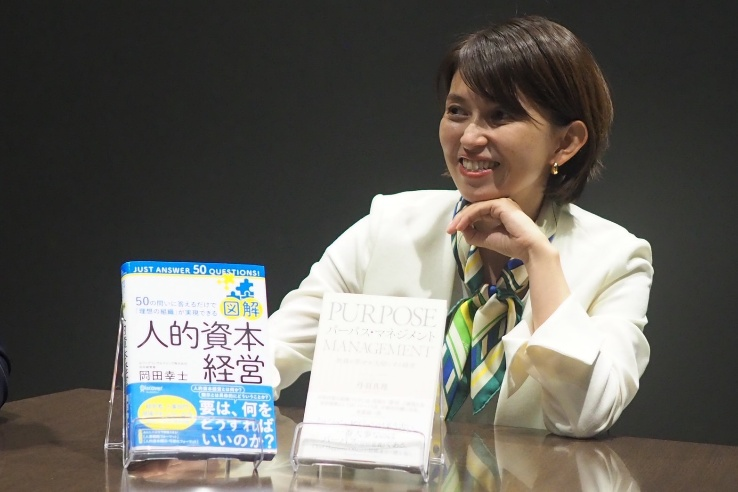
原田:よかったです。ギブできる部分がありそうで。でもおっしゃる通り、Luvirがどこまでやっている会社かと聞かれると、答えるのが難しいんですよね。
中川:「人・組織」領域を中心に、接客や戦略、業務改善もやっていて。ほんと、何でも屋みたいな感じですね。
丹羽:だから相談する側としては、「とりあえず聞いてみようかな」と思えます。
奥地:でもそれって、会社としての“エッジ”が見えづらくなってる原因にもなってて…。もう少し打ち出し方を整理してもいいのかも。
中川:そうなんですよね、「うちのコンサルティングって何?」って聞かれると、定義しづらい。
岡田:じゃあ、アイディールさんにお願いして、うちの「存在意義」とか「何者か」を言語化してもらいましょうか。相互理解も進みそうだ。
丹羽:それ、いいですね。面白そうです。
M&Aは組織文化の融合が鍵
中川:最近、M&Aとか組織統合が増えていますけど、そういった関連のご相談はあるんですか。合併したけど、組織の文化の融合がうまくいかないとか。
丹羽:ありますね。M&Aに限らず、組織が縦割りになっちゃってたりとか。
中川:いま、買収された側の従業員と本社側の人がなかなか交わらない、文化が噛み合わないといったケースがすごく多いんです。じつはLuvirでは、こういったM&Aの領域にも積極的にビジネス展開しようと思っていて。
丹羽:融和について、ですか?
中川:はい。そう思ったきっかけとしては、前職でライザップにいた頃。当時たくさんの企業買収を行っていたんですが、現場に入ると「本社から来たな…」と、よく思われていない雰囲気を感じたんですよ。
丹羽:微妙な空気になるんですね。
中川:そうなんです。でも、これは僕の感覚的な問題だけではなくて。実際にデロイトのレポートでも、M&Aの約3件中2件が失敗に終わっていると言われています。
その主な理由が「組織文化の融合がうまくいかない」ことなんですよね。文化の違いから、キーパーソンが離脱してしまったり、連携が機能しなくなるケースが多いんです。
だからこそ今、制度設計などのハード面(PMI)だけでなく、「人と文化の融合(=BMI:Behavioral & Mind Integration)」にも重点を置いたサービスを立ち上げたいと考えています。そのあたりも、まさにアイディールさんとご一緒できるポイントかなと。
丹羽:絶対ニーズがあると思いますね。M&Aに限らず、縦割り組織同士が交わらないケースや、文化の違いが壁になるような場面でも。
最初の段階でありがちなのが、経営陣同士が腹を割って話せていないというケースです。こうなると、現場にどれだけ浸透を図っても、結局は形だけで終わってしまう。だからこそ、経営陣の信頼関係や連携=「チームビルディング」の支援も、非常に大切なポイントだと思っています。
中川:分かります。ある企業の話なんですが、買収した初日に社長が現地に行って、「今日からよろしくお願いします。一緒に頑張りましょう」と一言だけ言って終わったんですよ。正直、「これか…」と思いました。
その一言で終わるということは、その社長自身も、組織の融和についてまだ意識が向いてないんですよね。本来M&Aって、企業にとってプラスに働く「変革のチャンス」であるはずなんです。それなのに、その変革によって社員が不幸になるという起きてはいけない動きが出てきているので、これは日本の課題だと思っています。
岡田:たしか丹羽さんのところでは、パーパスでもウェルビーイングを重視されてますよね。そこから派生して、「ウェルビーイングM&A」とか、ウェルビーイング関連で絡みがあっても面白いんじゃないかと思いました。
丹羽:ウェルビーイングM&A、面白そうですね!
共創を支える「文化の可視化」というアプローチ
中川:コンサルティング的なアプローチで組織文化の融合を進めていくことも重要なんですが、そこに加えて組織文化の融和を推進する「コンテンツ」があるとさらにいいなと感じています。たとえば、今の組織の状態を可視化するための文化診断ツールや、異なる文化同士の距離を縮めるためのワークショップ設計、あるいは研修プログラムなど。そうした、組織文化の融合を具体的に後押しする仕組みや仕掛けを一緒に開発して、提供できたら面白いですよね。
丹羽: じつは、最近出した「組織文化インサイト診断」というものがあるんです。組織文化を診断できるツールで、けっこう実用的なんですよ。
中川: えっ!そうなんですか。それって、どうやって開発されたんですか?
丹羽:うちのチーフ・カルチャー・オフィサーの宮森千嘉子というメンバーが中心になって開発したんですけど、彼女は「文化と経営の父」と呼ばれるホフステード博士の理論をもとにしていて。国ごとの文化の違い——たとえば日本人とアメリカ人の価値観の違い——みたいな話を、組織や個人に落とし込んで使えるようにしてるんです。ツールは、書籍『強い組織は違いを楽しむ』の付録として出しています。
中川: どんな風に診断できるんです?
丹羽: 個人用のアセスメントツールとして、6つの文化的な軸に基づいて自分の思う自組織の傾向が見えるようになっています。たとえば「曖昧さに対する許容度」とか「長期思考か短期志向か」「トップダウンが好みかフラットが好みか」とか。診断することで、現状、自組織はどんな組織文化になっているかがわかり、今後はどんな状態を目指していきたいかを考えるきっかけとなります。また、同じ考え方で、個々人の傾向も診断できるアセスメントもあります。こちらは診断を受けると、各軸で自分がどこに位置しているかがわかるんです。ちゃんと個人レポートも出ますよ。
中川: それ、すごくいいですね!
丹羽:個人のアセスメントについては、例えば経営陣に診断を受けてもらうと、「あの人適当でイライラするなあ」と思っていたのが、そういうのが好みだったのかと分かったり。価値観の違いが分かると、相互理解が進むんです。
中川:なるほど。その診断って、最終的には個人と組織のカルチャーが合っているかどうかまで分かるんですか?
丹羽:はい、合うかどうかもわかりますし、組織の「現在地」も把握できます。6次元モデルを使って、文化的な特性を可視化するんです。
中川:へぇ。こういうこと、僕達もやってみたいですね。
丹羽:こうした診断を通じて、「今はこういう文化だけど、将来的に目指すビジョンに向けてパフォーマンスを上げていくためには、こういう文化にした方がいいよね」といったことを皆さんで話し合ったりするんです。そして、そこに向かうためには「何を変えていく必要があるのか」「どんな取り組みが必要か」まで落とし込んでいきます。
中川:M&Aの場面でも活用できそうですよね。たとえば、買収先の文化と自社の文化がどう違っていて、それが統合後、こういうところがリスク要因になりそうだ、とか。
丹羽:そうですね。こうした診断で、双方の文化的スタイルがどう違うのかを明確に可視化できますし、その上で、「じゃあどうやって新しい文化をつくっていくか」というアクションに落としていく。どちらか一方に合わせる、という話ではないんです。
中川:そういうプロセス自体をファシリテートしながら、一緒に変革を進めていくような取り組みができたらいいですね。
丹羽:ええ、まさに。
奥地:そこに事業戦略や事業ステージの要素が加わってくると、より立体的になりそうだ。
岡田:あとはリーダーシップスタイルも、組織文化に大きく影響を与えますよね。
パーパス経営の3ステップの強化や、相互派遣、ウェルビーイングM&Aなど、それぞれの口から次々に語られる、具体的な「協業」のビジョン。
次回は、岡田氏が目指す理想の職場像がどのように作られているのか、アイディールの組織運営に迫る。


